【B#185】賢い人ほど、なぜ愚かな間違いをするのか?〜知性の罠に陥らないために
Table of Contents
はじめに
東京・渋谷でロルフィング・セッションと脳科学から栄養・睡眠・マインドの脳活(脳科学活用)講座を提供している大塚英文です。
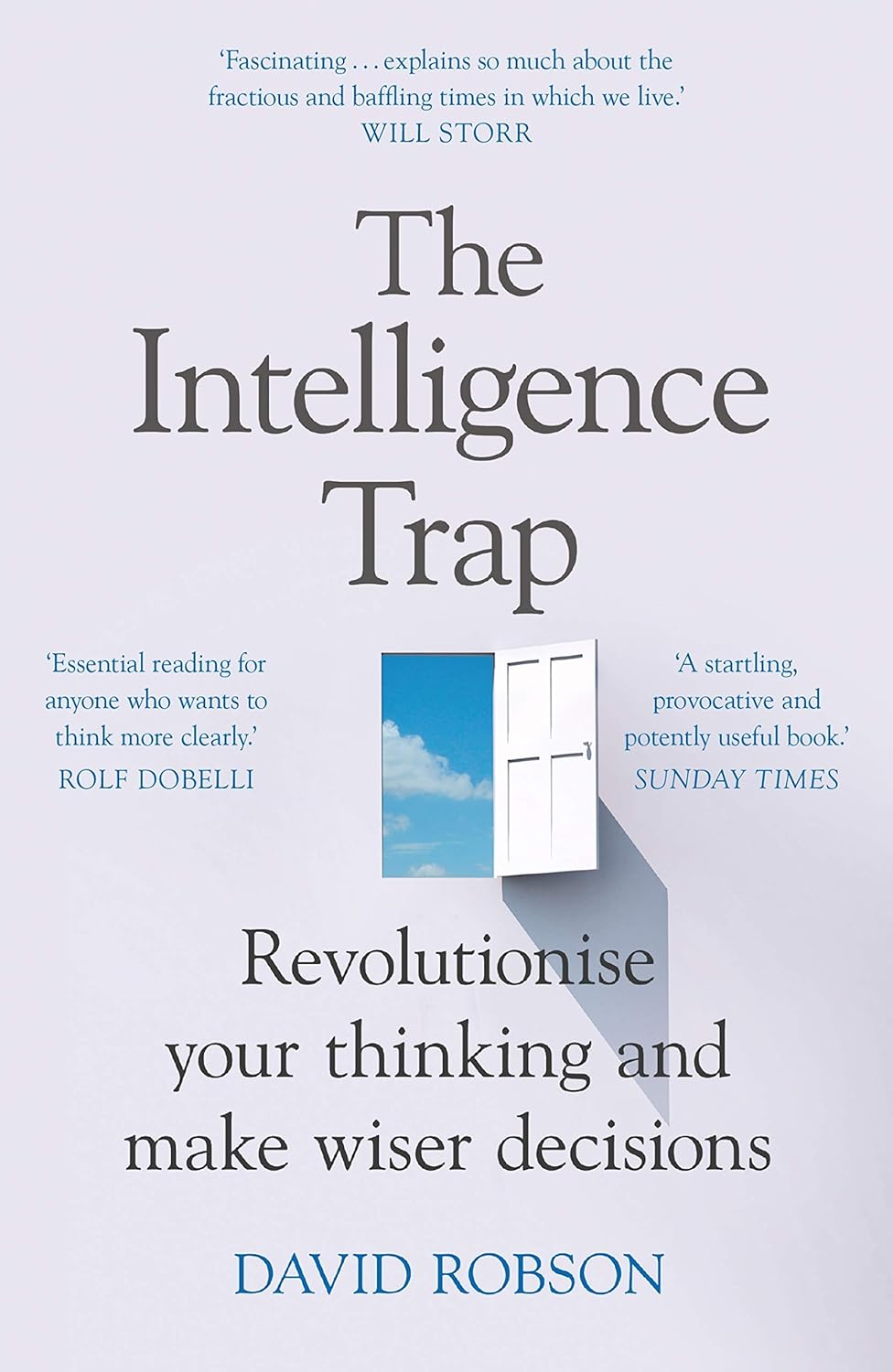
今回は、イギリスの科学ジャーナリスト、David Robsonによる著書『The Intelligence Trap(邦訳:なぜ、賢い人ほど愚かな決断を下すのか)』をもとに、「知性とは何か? なぜ賢い人ほど判断を誤るのか?」という問いに迫っていく。
「知性」が裏切る瞬間
現代社会では、IQや論理的思考力、学歴といった指標が「知性」とみなされることが多い。しかしRobsonは、そのような通念に異議を唱える。明らかにしたのは、高IQや専門知識の豊富さが、必ずしも賢明な意思決定につながるわけではないという逆説的な現実である。
“The most intelligent people are often the most vulnerable to the intelligence trap.”
「もっとも知的な人々こそ、知性の罠にもっとも陥りやすい」
つまり、知的能力が高い人ほど、自らの思考を過信しがちで、視野を狭めてしまい、結果的に誤った判断に陥る危険が高くなるということだ。
知性の罠:4つの心理的メカニズム
Robsonは、「知性の罠(The Intelligence Trap)」を生み出す要因として、4つの心理的傾向を挙げている。
1. スキーマ(Schema)による視野の狭まり
スキーマとは、過去の経験から形成された思考の枠組みである。情報処理の効率を高める一方で、既存の枠組みに固執することで、新たな視点を排除するリスクを伴う。
専門家ほどスキーマに強く依存する傾向があり、誤診や判断ミスにつながりやすい。
例:医師が以前の成功体験をもとに誤診を下すことがある。
2. モラル・アルジェブラ(Moral Algebra)による自己正当化
これは、自らの行動を「道徳的に帳尻を合わせる」心の仕組みである。
高い知性を持つ人ほど、論理的な整合性を使って自己矛盾をうまく合理化してしまうため、道徳的な盲点に陥りやすい。
例:環境活動家が、自家用ジェット機の使用を「全体への貢献」で正当化する。
3. 感情と身体の無視
知的な人は、論理やデータを優先するあまり、感情や身体感覚(エモーショナル・コンパス/身体マーカー)からの重要なシグナルを無視しがちになる。
例:数字上は有望な投資案件でも、「なんとなく嫌な予感」を軽視して失敗することがある。
4. 認知バイアスと過信
専門性が高い人ほど、自己の判断力への信頼が強くなり、確証バイアス(自分に都合のいい情報ばかり集める)や過信に陥りやすくなる。
例:長年成功してきた経営者が市場の変化に対応できず、大きな判断ミスをする。
知性と成功のギャップ:「ターマイト研究」の示唆
1920年代、心理学者ルイス・ターマンが実施した「ターマイト研究」は、IQが高い子どもたちの追跡調査であった。彼は、彼らが将来偉大な業績を成し遂げると予測したが、実際に顕著な成功を収めた者は少数にとどまった。
“Intelligence, by itself, is not a guarantee of a fulfilled or meaningful life.”
「知性それ自体が、充実した人生や意味ある成功を保証するわけではない」
Robsonは、人生の質や成果には、感情的柔軟性や人間関係のスキルといった“非IQ的要素”がより重要であると述べている。
実例1:福島第一原発事故 ― 専門家の過信
福島第一原発事故では、津波によるリスクは一部の専門家に認識されていたが、「発生の可能性が極端に低い」として軽視された。「過去に問題がなかった」というスキーマと、技術への過信が判断の柔軟性を奪った結果である。
この事例は、豊富な専門知識がむしろ新たな警告を無視させてしまう危険性を如実に示している。
実例2:NASAチャレンジャー号爆発 ― 集団的知性の罠
1986年、NASAのチャレンジャー号は、打ち上げ当日に技術者からの警告が出ていたにもかかわらず、管理層は計画を強行し、爆発事故が発生した。組織としての「成功してきた歴史」がスキーマとなり、意思決定の硬直化とモラル・アルジェブラが働いた象徴的なケースである。
論理の罠:「もつれた議論」と「知識の呪い」
知性の高い人ほど、複雑で一見筋の通った「もつれた議論(Entangled Arguments)」を構築できてしまう。
その結果、自他ともに誤った方向へ論理的に説得してしまう危険がある。
また、知識の呪い(Curse of Knowledge)とは、一度知ってしまったことを「知らない人の視点」に戻って考えるのが難しくなる傾向である。教育現場や企業のリーダーシップで、この罠が原因でコミュニケーションが断絶することは少なくない。
真の知性とは何か?
Robsonは、「真の知性(wisdom)」とは単なる情報処理能力ではなく、柔軟性・謙虚さ・感情や身体感覚との統合に支えられた思考力であると定義している。
“Wisdom is not about what you know but how you think.”
「知恵とは、何を知っているかではなく、どう考えるかである」
そのために必要とされるのは以下の4つの力である:
- 知的謙遜:自分が誤っているかもしれないという姿勢を持つ
- 認知的柔軟性:視点を変え、新たな可能性を受け入れる
- 反省的思考:自分の思考プロセスを客観的に見直す力
- 感情・身体の統合:頭だけでなく「全身で考える」態度
私たちは、どのように知性と向き合うべきか?
現代は、学歴や論理性が過剰に評価される傾向にある。しかしRobsonは、「考えることそのものを疑う力」こそが、本当の知性であると説く。
これは個人にとっても、組織や社会にとっても同様である。意思決定において、自分の「知っていること」に縛られず、他者の視点や感情、身体感覚を含めて判断する余白を持つことが、いま最も求められている。
推奨したい読者
この本は、次のような人々にこそ読んでもらいたい:
- 自分の判断や信念に確信を持ちすぎてしまう傾向のある専門家・エリート層
- 「正しさ」に固執してしまいがちな教育者や医師、リーダー層
- 感情や身体知と論理思考の統合に興味のある実践者
- 思考の柔軟性やメタ認知を鍛えたいビジネスパーソンやコーチ
少しでもこの投稿が役立つことを願っています。






